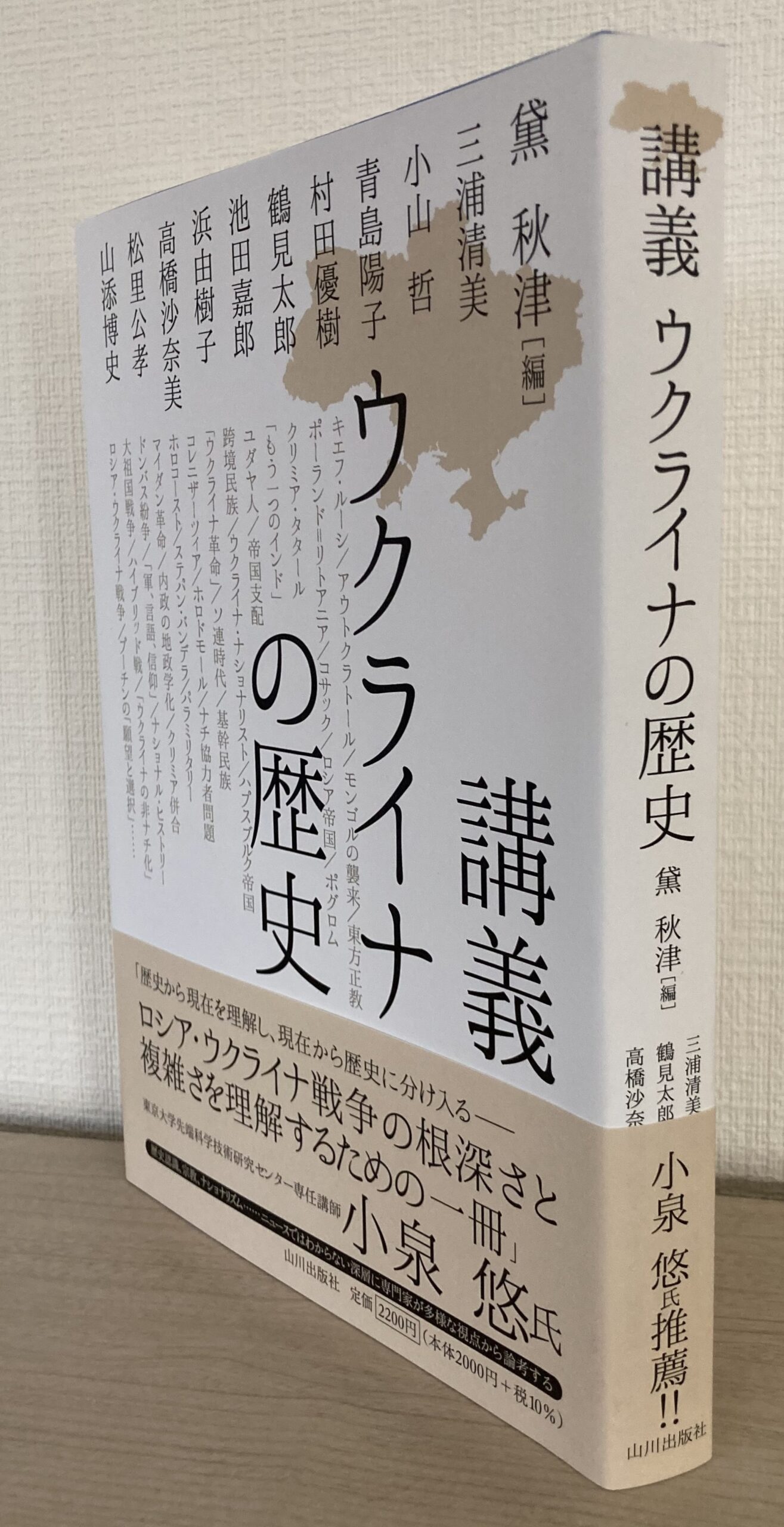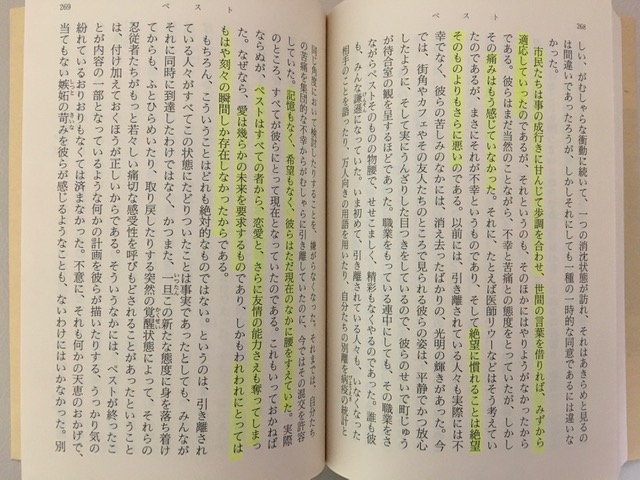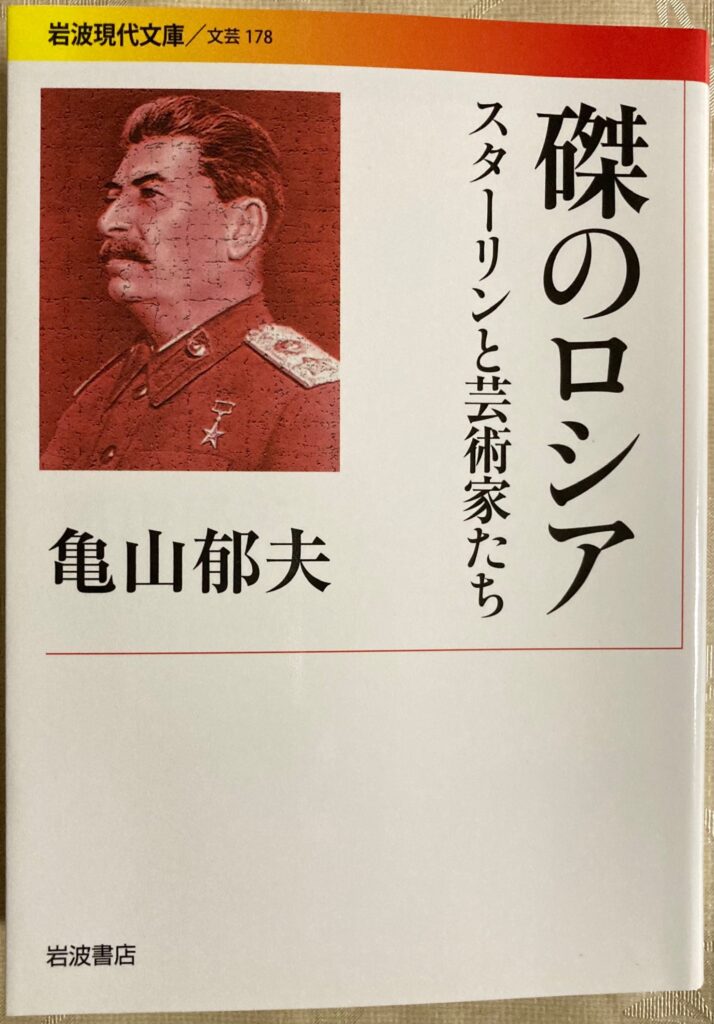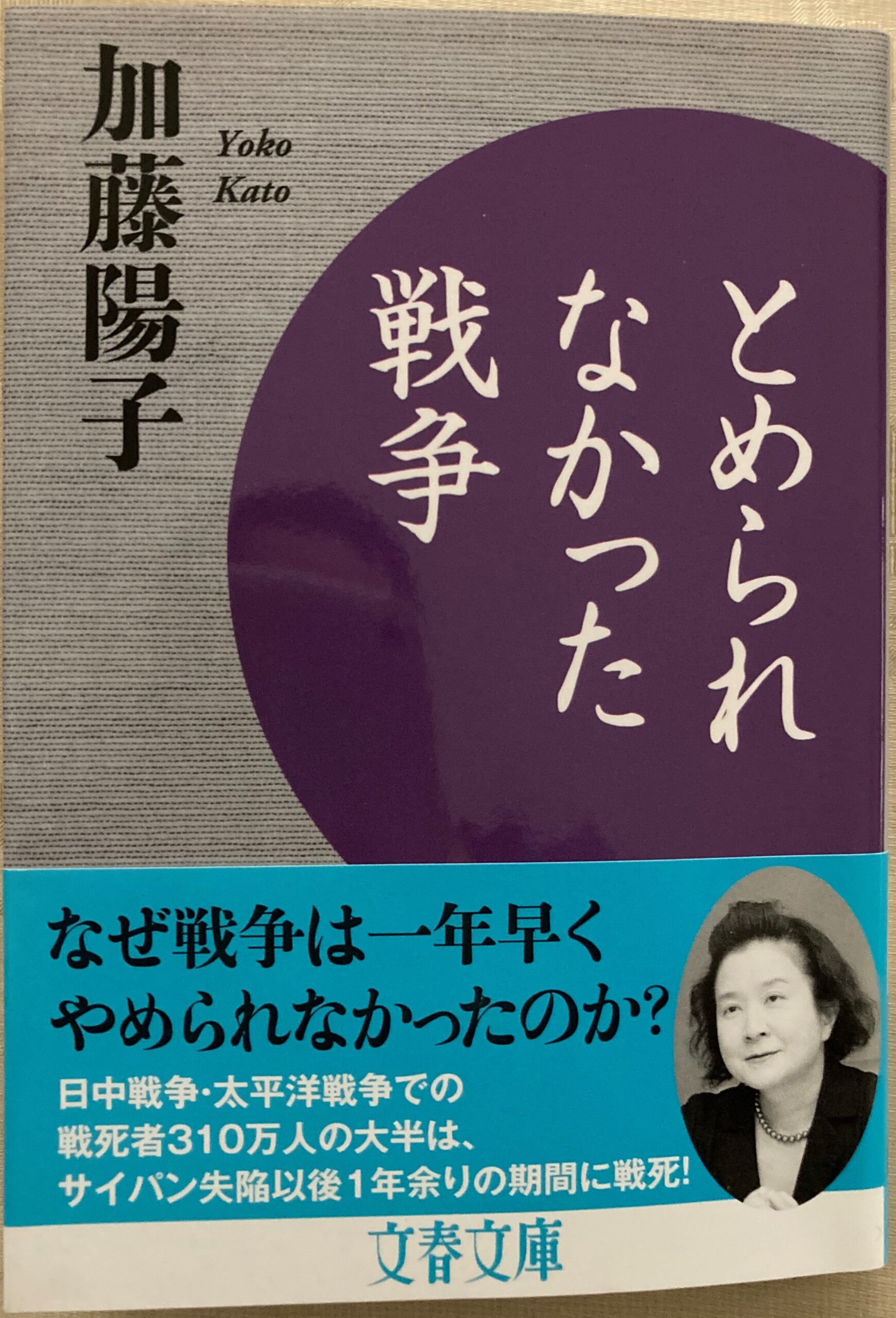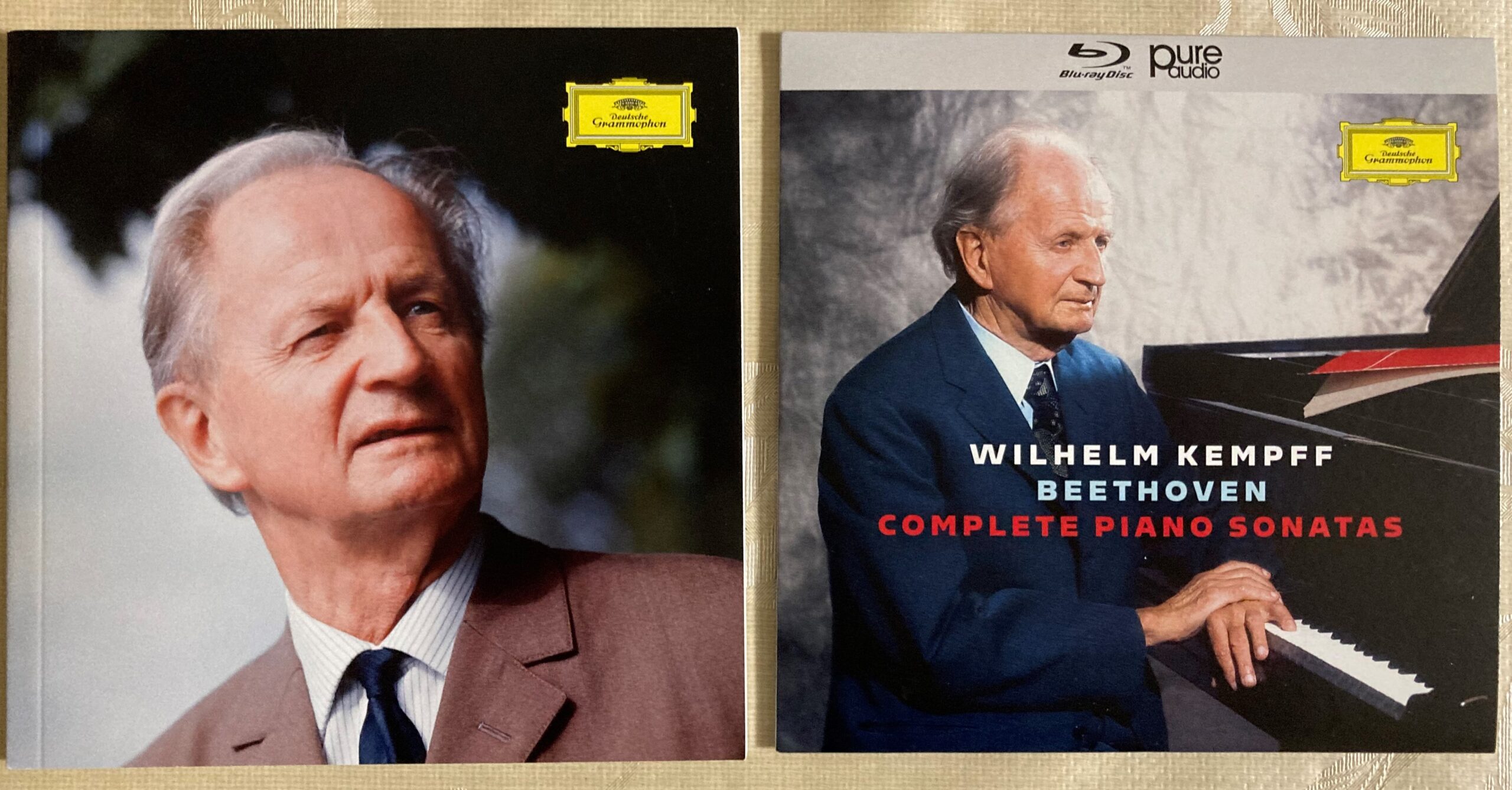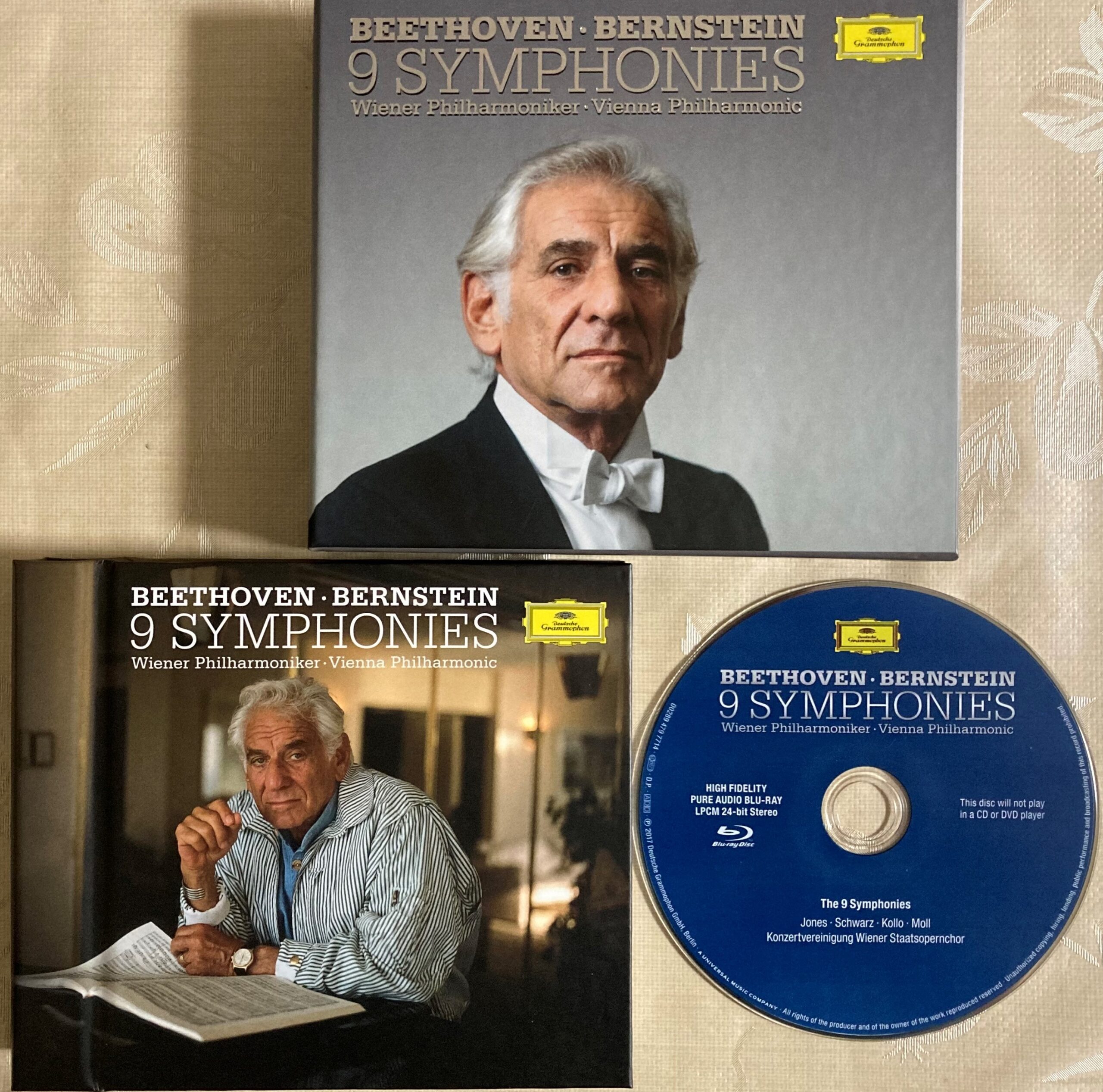目 次
開花したシャクヤクへのルーティン作業だが
10月も中旬となって、いよいよ来年のシャクヤクの開花に向けて準備する季節の到来だ。
来年に向けての新たなシャクヤク畑の造成と、そこに新たな苗を植え付けたことは既に報告したとおり。
今回はそんな新たな取組みではなく、例年お決まりのルーティンとしてやらなければならないことの報告だ。
その意味では地味な記事となりそうだが、今年は新たな少し思い切った試みをやってみて、それが興味津々の結果となったので、楽しみに読み進めてもらえるとありがたい。
スポンサーリンク
「花後」のシャクヤクはそのまま放置
先ずは、5月にシャクヤクの花が終わってから、完全に放置されていた「花後の処理」である。
5月末には完全に花が終わってしまったシャクヤクは、その後どうなっているのかご存知だろうか?あれから5ヵ月、品種によっては丸々半年経過している。
その間、シャクヤクは完全に放置され、そのまま庭と言うか畑に残っている。つまり花のない茎と葉っぱだけの状態で、約半年間そのまま植えられている。それが「花後」のシャクヤクの実態だ。
こんな感じで残っている。
【南側のシャクヤク畑】




【玄関側(北側)】

スポンサーリンク
光合成で地下の根に養分を送り込む
何故なのか?シャクヤクはあの豪華極まりない花が命なので、その花が終わってしまった後は、もう茎ごと伐採してしまえばいいじゃないか、そう思われても当然だ。
ヒマワリのように、花の終わりが、そのまま全体の終わりのように。
ところが、ヒマワリとシャクヤクとは翌年の生え方が全く異なる。単年草と多年草との違い。ヒマワリのような単年草は、一年に1回種を撒いて、その種から芽を出して成長していく。種を撒かないと、同じ場所から生えてくることは決してない。
シャクヤクは多年草。地下に株が残っていて、その株が毎年成長して大きくなっていく。毎年この地下の株から新芽が顔を出してくる。つまり放っておいても、毎年、新芽が顔を出してくる、非常にご機嫌な嬉しい花なのである。
で、花後の茎や葉っぱの放置の話しに戻る。放置と言っても、僕がやるべきことをやらないで放ったらかしにしているわけではない。シャクヤクは魅力的な花が終わった後の、何の魅力もないただの茎と葉っぱが実は、非常に重要な役割を果たしているのである。
ズバリ光合成だ。地上の葉っぱが光合成で養分を溜め込んで、地下の株と根にその養分を送り込むのである。そして地下の株が成長し、翌年の新芽、更にその後の立派な花を咲かせるべく今のうちに準備をしているわけだ。
したがって、花が終わっても、決して地上の葉っぱを伐採してはいけないのである。
だが、10月に入ると地上の葉っぱが変色し、やがて枯れてくる。その段階で伐採することになる。我が家の葉っぱを見ると、まだ青々としているが、一部は茶色に変色し始めており、伐採の時期に入ったと言えるだろう。
一般的にも10月の中下旬にかけて伐採するのが望ましいとされている。
スポンサーリンク
全て地表すれすれに伐採する
ということで、10月8日(水)に我が家の庭の全てのシャクヤクの茎と葉っぱを伐採した。
こんな感じでドンドン伐採していく。


スポンサーリンク
地表を少しほじって地中の新芽を確認
この茎と葉っぱの伐採の際に、今年は思い切ってあることにトライしてみた。
葉っぱの付いた茎を、地表から数センチの位置で伐採したそれぞれのシャクヤク。その茎が生え出している地表部分をホンの数センチ、優しくほじってみる。いや、ほじるというよりも地表の土をホンの少しだけ指でどかしてやるだけだ。
すると地中の中から、赤あるいは白い新芽を確認することができた!
これは、先日のWさんからソルベットを株分けしてもらった際、根っこの付け根というか脇の部分に多くの新芽が付いている姿を目の当たりにしたことで、他のシャクヤクもきっと同じように茎と根っこの付け根部分、脇にきっと新芽が付いているはずだと見込んだことによる。
もちろん株分けをするわけではないので、少し土をどかして新芽を確認するだけで、直ぐに土を被せて元に戻すことは当然だ。
Wさんのソルベットのようにもう20年近くに渡って完全に根付いているシャクヤクと、我が家のまだ一番長い物でも4年しか経っていないシャクヤクとでは決定的な違いがあって、この10月中旬に地中に新芽があるのか、全く想像すらできない。
それを確かめたくなった。
こうして、今年全く開花しなかった品種も含めて、全ての品種の根っこの付け根部分を確認してみたのである。
スポンサーリンク
今年咲かなかった品種にも新芽を確認!
するとどうだろう。何と全ての品種で、新芽を確認できたのである。
昨年植え付けたばかりで、今年は全く花が咲かなかった、いや、蕾すら付けなかった品種にも新しい芽を発見することができた。
先ずはそこから見てもらおう。
昨秋植付け、今年蕾が付かなかった品種。具体的には黄色シャクヤクの「楊貴妃」と移植もした「火祭」。
【楊貴妃】
これが「楊貴妃」の地中の新芽。
「楊貴妃」はちゃんと発芽して成長したものの、蕾を付けなかったどころか、背も伸びず、葉っぱもほとんど広がることもなく、とにかく非常にこじんまりとした心もとない品種だった。このまま枯れてしまうのではないかと心配していたものだ。
ところが地中には非常に力強い大きな芽が、ちょっと土をどかしただけで3個も確認できた。


【火祭】
こちらが「火祭」の地中の新芽の様子。
元々塀際の狭くて環境の良くない場所に植えていたのだが、「ソルベット」の場所を広めに確保するために、一旦、植え付けて葉っぱまで広がってきていたものを掘り返して、もっと奥の条件の悪い場所に移し替えた。
それだけに、ちゃんと地中の株が育っているか心配していたものだ。
それがこのとおり。赤く尖った新芽が直ぐに顔を現した。


【ソルベット】
我が家のソルベットは、一昨年、僕が大チョンボをやらかして地中の太い根を切ってしまったことで、今年は蕾を一つも付けてくれなかった。来年以降どうなるのか、全く予断を許さない状況。
今年、蕾が一つも付かなかったものの、茎も葉っぱも大きく成長してくれた。このたくさんの葉っぱの光合成の力で、来年は再び以前のとおり開花してくれるのかどうか?
地中の新芽はしっかり確認できた。


スポンサーリンク
今年開花の品種にはもちろん多くの新芽
後は今年開花してくれた品種ばかり。
同じ開花とは言っても、「ラテンドール」や「麒麟丸」、2つの「夕映」など、毎年たくさんの花を咲かせてくれるしっかりと完全に根付いてくれた品種と、何とか1~2輪だけ開花してくれたものと2つに分けられる。
先ずは何とか開花してくれた品種から見ていこう。
スポンサーリンク
1~2輪だけ咲いてくれた品種
これはドンドン写真で新芽を見てもらう。例外なく地中の浅い部分に新芽を確認することができた。
【かぐや姫】

【アレックスフレミング】

【サラベルナール】

【モーボクエン】

【波の華】
これは昨秋植え付けた新しい品種であったが、1輪だけとはいうものの、非常に印象的な外側だけが薄いピンクの純白の花を咲かせてくれたシャクヤクだった。
一般的に、植え付けた最初の年は、蕾が付いてもそれを開花させない方がいい、あくまでも地下の株を成長させるために養分を使うべきだ、と言われている。
いきなり付けてくれた立派な蕾を開花させるべきかどうか大いに迷ったが、やっぱり咲かせて良かったと思っている。気品のある本当に素敵な花だった。



初年度から咲かせると株の成長が鈍くなるということで、地下の状態が心配だったが、少なくとも3つのしっかりとした新芽を確認できた。きっと来年もしっかり咲いてくれるものと期待している。


スポンサーリンク
例年しっかり咲いてくれる品種
これらの品種に新芽が付いていることは、何も心配していなかった。これらの品種には地下に大きな株が育っていて、端っこの一部を確認しただけである。
【ラテンドール】


【麒麟丸】


【夕映:南側】

【夕映:玄関側】


スポンサーリンク
伐採後の姿を写真で確認
こうして地表すれすれの位置に育っていた地中の新芽を確認した後は、地表から4~5センチ残していた茎を全て地表すれすれの位置で伐採し、地表には何も残っていない状態にする。
その後は、ネームプレートが刺さっているだけのきれいに整った花壇が広がっているだけの姿となる。
何の変哲もない、雑草がすっかりきれいに除去された土で覆われた花壇だけの光景が広がるだけだ。
【南側のシャクヤク畑】


【玄関側】



スポンサーリンク
シャクヤク畑全体の最終の姿
最後にこの日(2025.10.8)の作業が終わった最終の姿を見ていただく。
新しく造成したシャクヤク畑には新たに購入した苗と、Wさんから株分けしてもらったソルベットが植えられ、今年開花したシャクヤクは全て茎と葉っぱが伐採されて、更地のようになっている。
その我が家のシャクヤク畑、シャクヤク花壇と言った方がハイカラだが、その現在の姿である。
【南側】



【玄関側】



スポンサーリンク