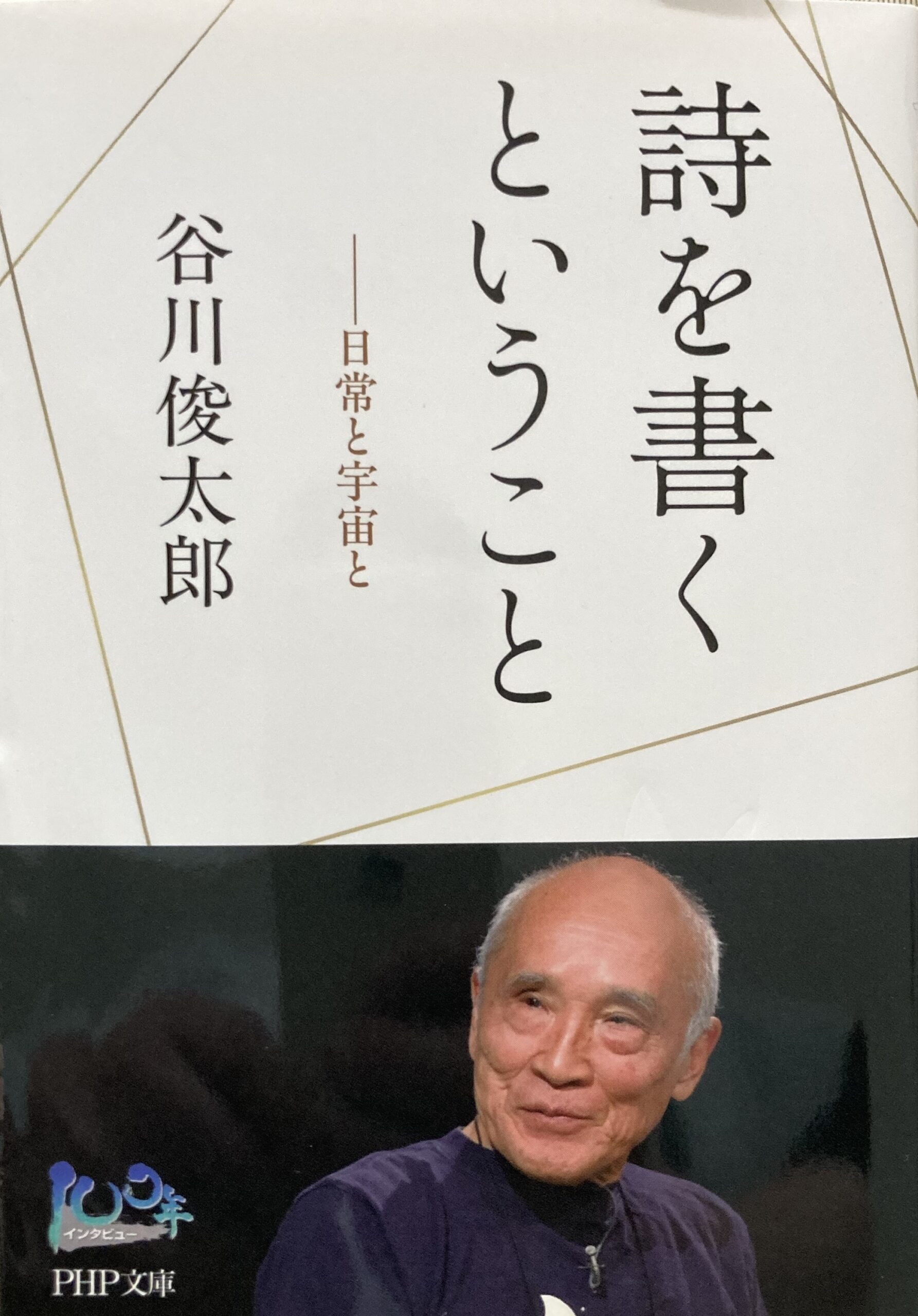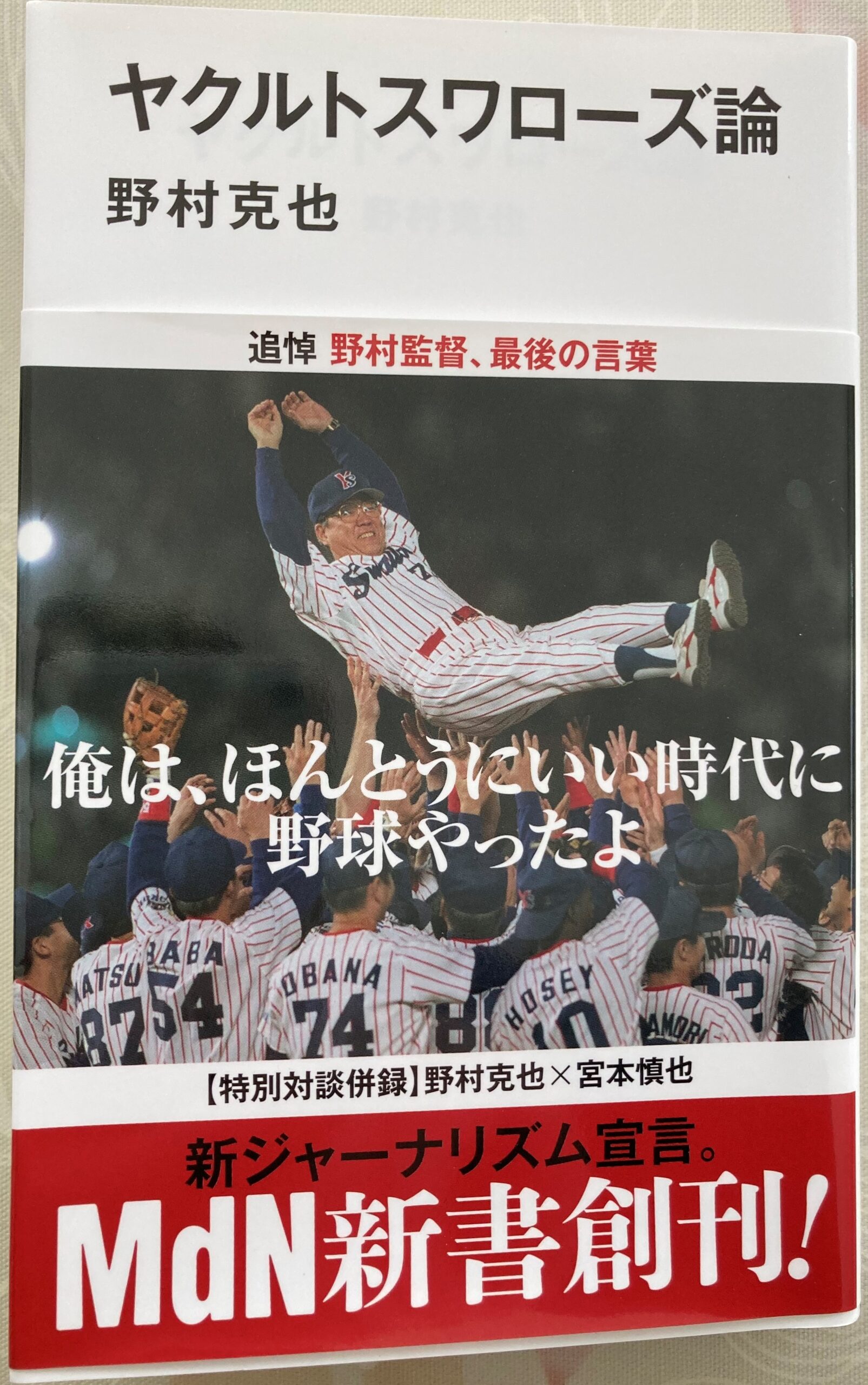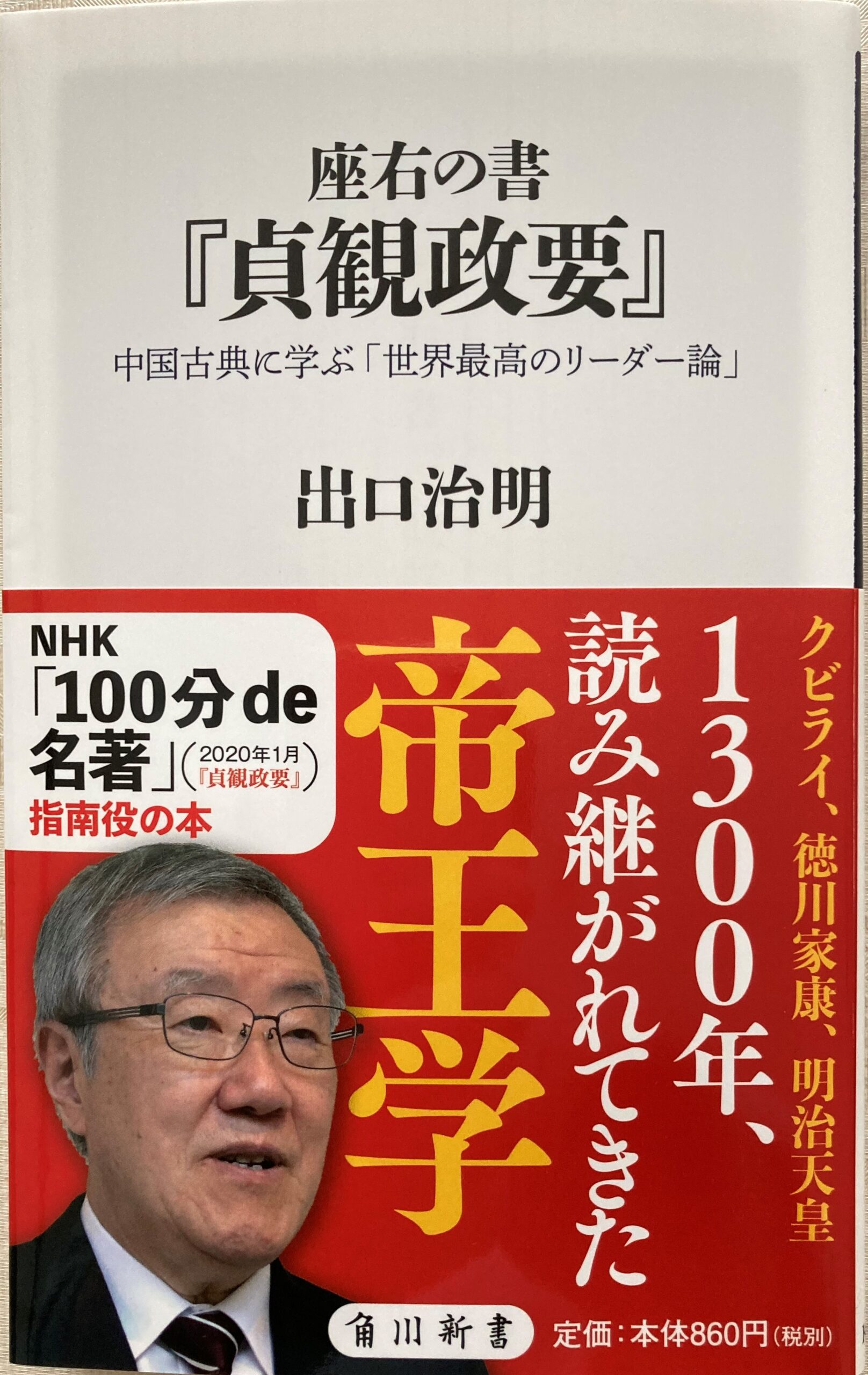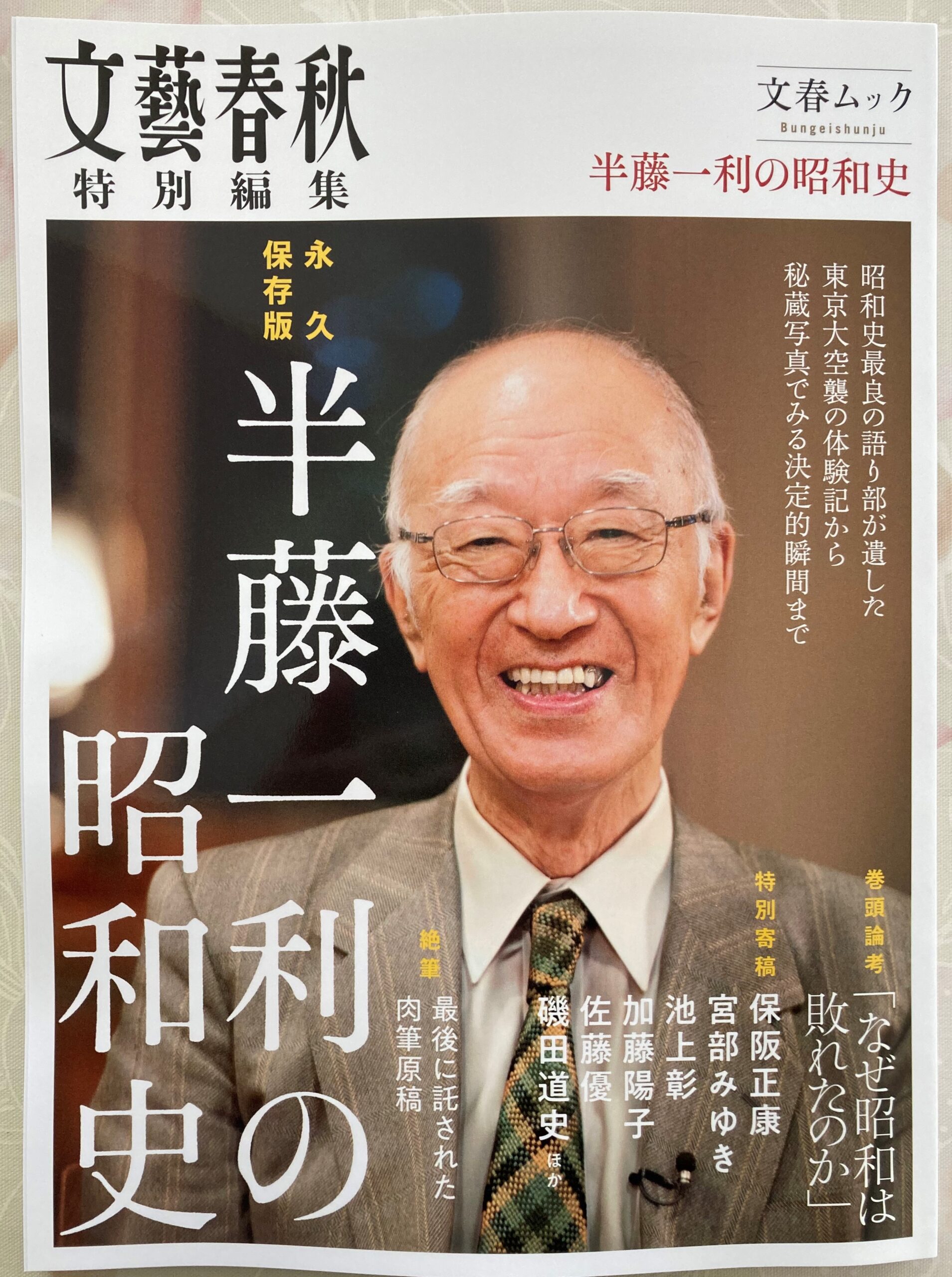「アドルフに告ぐ」については刊行に至るまでの様々な経緯やストーリー、漸く発売された超豪華本のオリジナル版に関してまで、その概要についてはほぼ語り尽くしたが、肝心の内容の掘り下げについてはほとんどできていないため、予告させていただいたとおり「ネタバレ」満載で掘り下げてみたい。
まだ「アドルフに告ぐ」をお読みになっていらっしゃらない方は、今回のこの記事はどうかスルーしてください。
「読んでから読む」でお願いいたします。
目 次
「アドルフに告ぐ」で一番考えさせられ、胸を切り裂かれるのは
深く感動させられたり、激しく衝撃を受けたりする場面が続出する「アドルフに告ぐ」にあって、全体を通じて物語の中核を形成するのは神戸で親友として共に過ごしたアドルフ・カウフマンとアドルフ・カミル。この二人のアドルフの物語であることは言うまでもない。ナチス党員の父と日本人女性との間に生まれたドイツ人のカウフマンとパン屋の息子のユダヤ人のカミル。この親友だった二人のアドルフの成長と友情の行方、最後には互いに殺し合うところまで行ってしまう愛憎が、このドラマの中核をなすが、何て悲痛な救いようのない物語なんだとうなだれるしかない。
この二人のアドルフの愛憎劇が、神戸での幼少期から、二人を激動に巻き込んだ第二次世界大戦が終了した後のパレスチナ紛争に至るまで約40年以上に渡って描かれるわけだ。その中であれだけ仲の良かった親友同士が、いかにして敵同士として殺し合うところに至るのか。ここが一番、考えさせられ、胸を切り裂かれる部分である。
スポンサーリンク
あんなに親しかった親友が憎しみ合うようになるのがあまりにも辛過ぎる
かたや日本人との混血とはいうもののナチスの幹部を父親に持つドイツ人のカウフマンと、ユダヤ人のカミルとが少年時代に親友同士だったということ自体がそもそも有り得ないことだった。二人は神戸で親しくしていた当時から、周囲からはお互いに付き合うなと大人の理屈を突きつけられていた。それにもかかわらず、二人は無二の親友だったというところが先ずは泣かされるところだ。父親がドイツに連れて行ってヒットラーユーゲントに入学させようとするのをトコトン嫌がり、思い切って必死の家出までして抵抗するカウフマン。このくだりは、後の展開を知っているだけに何よりも胸を打たれる。こんなにまで純粋で、カミルとの友情をカウフマンは大切にしていたのだ。それなのに・・・・。
そんな二人の友情を強引に引き離そうとする父親とナチスの幹部たち。このあたりはあまりにも辛過ぎて、僕はいつもまともに読めなくなってしまう。
強引にドイツに行かされたカウフマンはナチス党員として英才教育を施されていく
う~ん、辛い話しだ。ユダヤ人の親友がいたカウフマンはナチスの教えをおかしいと思いつつも、いつの間にかナチスの教育に染まっていってしまう。ここが物語を通じて僕が一番恐ろしいと思う部分だ。元々まじめで優秀なカウフマンは、純粋なドイツ人ではないとして周囲から疑惑の目で見られるために、それを打ち払うためにも優等生としてナチス教育を受け入れざるを得ないという二律背反を背負っていた。ここで頭角を現すしか自身のアイデンティティを確立することができなかった。かわいそうなカウフマン。二律背反に苦しみながらもカウフマンはメキメキと才能を発揮し、遂にはヒットラーその人にも気に入られ、ヒットラーの秘書(見習い)にまで出世していく。こうしてカウフマンはすっかり洗脳され、ユダヤ人を虫けら以下だと信じ、何のためらいもなく殺戮できるところまでマインドコントールされてしまう。
そのときから二人の悲劇は始まった。手塚治虫も一体何という人だろう。日本人の血が混じったカウフマンの忠誠心を試すために、最初に殺させるユダヤ人に、わざわざよりにもよってカミルの父親を選ばせるなんて。これはあまりにも残酷過ぎる。
昨年公開された話題の映画「ジョジョ・ラビット」では、ヒットラーユーゲントでの訓練で、ウサギを殺害させるように命令されるのだが、40年以上前の手塚治虫の漫画では、容赦なくいきなり大人のユダヤ人の殺害だ。手塚治虫は全く容赦ない。それも親友の父親。これはあまりにもむご過ぎるシーンだが、これが最後の最後まで二人の間の決定的な憎しみの原因となってしまう。
だが、カウフマンは自ら望んでカミルの父親を殺したわけではない。ナチスが、歴史がそうさせたのだ。むごい。むご過ぎる。
洗脳教育・マインドコントロールの恐ろしさは何時の時代にもあり得る
ここが「アドルフに告ぐ」で最も感慨深いテーマ。教育と洗脳、マインドコントールがいかに恐ろしいものか。これはいつの時代にもあることで、「アドルフに告ぐ」の中でも日本の戦前の一般庶民の感情をいかにも見事に描いている。小城先生の実家の兄。自分の家からアカ(共産党員)を出すわけにはいかない。そんなことになるなら肉親でも殺してしまった方がいいという発想。この時代の全体主義(ドイツのナチスやイタリアのファシスト党、そして日本の皇国史観に基づく軍国主義)は本当に個人の素直な感情を全て捨て去らせ、見事なまでに国民全体にマインドコントールを施したのだった。
戦後でもそう。連合赤軍のなれの果ての仲間同士による総括という名の殺し合い。そして何と言っても記憶に新しいのはあのオウム真理教だ。あれほどまでに優秀な若者たちが、みな洗脳され、マインドコントールを受けて、松本サリン事件と地下鉄サリン事件を引き起こし、その前には坂本弁護士一家を無残にも殺害した。その他諸々の凶悪犯罪。
いずれも誤った教育のせい。洗脳教育というものの恐ろしさをまざまざと思い知らされる。

アドルフ・カミルの不自然なまでの豹変ぶりは
いきなり物語の最後に飛ばさせてもらう。最後に待ち受ける衝撃は、あのアドルフ・カミルの突然の豹変ぶりだ。これがいかにも唐突で少し不自然。ある意味で最もまともでバランスの取れた健全な精神の持ち主であったカミル。手塚治虫自身の言葉を借りれば「平和主義者」だったカミル。それがどうしてカウフマンに勝るとも劣らない殺人鬼になってしまったのか。
ここは相当に賛否が分かれるところだと思う。アドルフ・カミルの急な変貌以前の話しとして、そもそもあのパレスチナの下りは蛇足、不要だったのではないか。第二次世界大戦、日本の終戦と共に終了させた方が良かったのではないかという考え方だ。
僕は最初にハードカバーで読んだ際、このイスラエルとパレスチナの下りは要らなかったな、これは止めてほしかった。実際にそう感じたことを正直に告白しておく。今では考え方は変わっており、やはり不可欠だったのではないか、手塚治虫にとってはむしろこの最後のくだりを抜きにしてはどうしてもこの物語は終わりにさせることはできなかったのではないかと考えている。
そもそもこの名作のタイトル「アドルフに告ぐ」というのは、最後の最後、凶悪なイスラエル兵となったカミルに自分の妻と娘を無残に殺されたカウフマンが最後の決着をつけるべく、カミルを呼び出す時に貼ったビラの言葉だったのだ(厳密にはもう一カ所出てくるのだが)。ということは、手塚治虫はこの連載をスタートさせたときから最後のこのエンディングはこう決めていたことを表している。
逆に言うと、あのイスラエル対パレスチナの対決を描くために、延々とこれだけの壮大な物語を紡いできた可能性すらあるのだ。
スポンサーリンク
原因の一因は手塚の入院による連載中断にあった
手塚治虫は、週刊文春での連載の終盤で胆石等の治療のために約2カ月間近くの連載中断を余儀なくされた。ご本人の言葉でもこの中断を非常に残念に思っていたようだ。これだけのカリスマ大漫画家の注目の連載なのだから、そのまま2カ月間、延長してくれれば済むことじゃないかと簡単に思ってしまうのだが、そういうところが素人の浅はかさなのだろう。
手塚治虫の解説によれば、あの2カ月間の連載中止で当初の予定が狂い、あの僕が唐突と感じたイスラエルとパレスチナとのくだりが描き切れなかった。中断されることがなければもっともっとページを割いて、詳しく書きたかったらしい。それは返す返すも残念なことだった。
それでも手塚治虫は連載が終了し、単行本化される際に、かなり加筆している。そのあたりは例の「オリジナル版」を読んでいただけるとその違い等もハッキリとするのだが、その単行本化の際の加筆修正でも手塚治虫は、まだ描き足りなかったようだ。確かにもっと描いてくれれば、その中にあのカミルがどういう経緯で血も涙もない殺人鬼に変貌していくのか明らかになったはずなのだ。
だが、僕は今ではこう考えている。
イスラエルという国の在り方がカミルの変貌そのものを象徴しているのでは
カミルの急な豹変、変貌はイスラエルそのものではないか。そう思わざるを得ない。
あのナチスに虐殺されたユダヤ人たちが戦後、自らの国イスラエルを建国し、その後のイスラエルの周囲のパレスチナ諸国への極めて強権的かつ横暴な姿勢を見れば、その変貌そのものが、カミルの変貌とそっくり重なってくる。カミルの変貌とユダヤ人がイスラエル建国後の変貌とが見事なまでに二重写しになってくるのである。
カミルはユダヤ人とイスラエルという国家の象徴として描かれているのではないだろうか。
したがって、僕たちは読者は、これはアドルフ・カミルの変貌、豹変というよりもむしろイスラエル、つまりはユダヤ人の変貌と捉えるべきなのだろう。そう考えるとこの「アドルフに告ぐ」の中での唐突とも言えるカミルの豹変は決して不自然ではなく、むしろこの豹変こそ物事の本質だったということになる。このあたりは色々な解釈と感じ方がありそうだ。「アドルフに告ぐ」ファンの皆さんのご意見を是非聞いてみたい。
スポンサーリンク
どうして全ての恋が、いつも一目ぼれから始まるんだ!?
もう一つ「アドルフに告ぐ」でどうしても引っかかり、これはたまらんなと思うのが、物語に登場するいくつもある男女の恋愛関係が、全て一瞬のうちに恋心が芽生える「一目ぼれ」で始まってしまうこと。この「アドルフに告ぐ」の中のどうしようもないマイナス点だと初めて読んだときから感じてきた。
この長大にして壮大な物語の中にはいくつもの恋愛が描かれている。
具体的に、「アドルフに告ぐ」の中で描かれる恋愛関係を列挙してみる(一目ぼれの一覧)と、
① アドルフ・カウフマンがユダヤ人の娘エリザに一目ぼれ(ドイツにて)
② アドルフ・カミルが同じくエリザに一目ぼれ(神戸にて)
③ 神戸のドイツ総領事館のナチス高官の妻だったカウフマンの母親の由季枝が峠草平に一目ぼれ
④ 峠草平の恩人である仁川刑事の娘八重子が峠草平に一目ぼれ
⑤ 同じく八重子がゾルゲの協力者だった本多芳男に二度目の一目ぼれ
⑥ 若狭追ヶ浜のおかみお桂が峠草平に一目ぼれ
何とこれだけあって、その全てが会った瞬間に相手を好きになってしまうという展開だ。これはちょっとダメだなと思う。ハッキリ言って雑だ。そう言われても反論できないだろう。
そしてこれらの一目ぼれから始まる恋愛感情が物語の展開に決定的な役割を与えているだけに、残念でならない。単なる一エピソードに留まるものではないのだ。
ちなみに、②のカミルのエリザへの思いについては、カミルの母親がズバリ本人に「おまえ、もしかしてあの娘さんに一目ぼれしたんじゃないかい」と訊ねる場面がある。手塚治虫自身、一目ぼれを認識していた証で僕にとっては衝撃的な発言。ちなみに手塚治虫は、この会話で「一目ぼれ」との表記を使っており、僕は「一目惚れ」と「惚」の字を使いたいのだが、手塚治虫に合わせている、念のため。
これは何とかならなかったのだろうか?ここだけは大いに不満
だが、翻って良く考えてみるに、やはり男女の仲は、一番最初は一目惚れから始まるのかな?と思わなくもない。だが、あの中国の文化大革命を描いた不朽の名作映画、謝晋監督の「芙蓉鎮」のように、最初に巡り合ったときにはどうってことのない関係だったのに、互いに苦楽を共にするうちに少しずつ愛が芽生え、やがてそれが大きく膨らんできて真の恋愛に至るという愛を描いてくれなかったのか、と残念でならない。
この「アドルフに告ぐ」は手塚治虫自身が「あとがきにかえて」の中で「この話は本当は恋愛ものじゃないかと思うんです。だから、もっと女性向きに描けたのかもしれません」「そういう、恋愛のさまざまなパターンを織り交ぜて描いていったら面白かっただろうと思うんですが、時すでに遅し、でした。云々」。
手塚治虫にそこまでの思いがあったのなら、その全てが一目ぼれで始まるのではなく、せめて一つくらいはじっくりと時間をかけて育まれるような恋愛を描いてほしかったと愚痴の一つでもこぼしたくなる。本当に残念でならない。
実は、手塚治虫が描く恋愛は得てして一目惚れから始まることが多い。手塚治虫という人がそういう人だったのかなと思われなくもないが、作品の中には「ばるぼあ」や「どついたれ」など時間をかけてだんだんと相手を理解し、愛が育まれていくという物語も少なからずあるだけに何とかならなかったのだろうか、というのが熱烈なファンの率直な思い。
スポンサーリンク
親しい友人は、人物描写と心理描写が少々雑だと不満を口にするが
僕の親しい友人は、この「アドルフに告ぐ」の抜群のおもしろさを認めつつも、人物描写と心理描写が少々雑だと不満を感じているようだ。序盤の峠草平が弟の恋人(あのゲシュタボの幹部ランプの娘)がナチスのスパイであったことが判明し、弟も自分のことも騙していたと怒り狂い、真相を激しく追及する中で、最後には強姦に至る問題のシーン。その直後に娘はビルから投身自殺するのだが、そのことに対してあれだけ情の厚い、優しい熱血漢の峠草平が心を痛めていないことを一例として挙げている。
友人自身、細かいことだと言っているが、そう感じるのは分からなくはない。一方、終盤に日本に戻ってきたカウフマンが自分が助けたエリザが何とカミルと恋仲になり婚約したことが分かり、エリザが自分の思い通りにならないと知って強姦してしまう。これはあまりにも単細胞なのではと言うのである。
強姦シーンに感じる女性読者の鋭さか
これは奇しくも若い女性が強姦されるという「アドルフに告ぐ」全体をとおして2カ所しか出てこない強姦シーンで、そのように感じたのは、もしかしたらその友人が女性であることと関係しているのかもしれない。正直言って僕にはそれほど不満は感じないシーンだったから。
最初の峠草平のランプの娘へのシーンは、一言で強姦と呼ぶには微妙なもっとデリケートな場面であり、しかも峠の怒りの深さは十分すぎるくらい分かるだけに少し肩を持ってしまう。それと、あのランプの娘の投身自殺は峠に「強姦」されたから死んだ、そんな単純なものとは思えない。恋人だった峠の弟と峠自身を騙した罪の意識と、一方でゲシュタポの大幹部の父親との板挟みに苦しんだ上での彼女なりの答え。僕は峠の弟に対する罪の意識と愛と誠意の証ということが決定的だったのではないかと感じている。
また一方で、峠がランプの娘の自殺に対して全く心の痛みを感じていなかったのだろうか?と言うと決してそうではないような気がしてくる。明確なシーンは出てこないが。これは身びいきな解釈だろうか。
終盤のカウフマンのエリザへの強姦は、これはまごうことなき強姦で、弁護の余地は一切ない。この時点でもうカウフマンはとっくに怪物、悪魔に変貌を遂げているのである。ユダヤ人を無慈悲に殺戮することに全く抵抗を感じなくなったカウフマンが、自分が命を助けてやった娘に対して強姦をするくらい、いともたやすいことだ。しかもエリザはユダヤ人なのである。いくら自分が愛する女性だとしても。彼はそうやって強姦すればカミルとの結婚は結婚できなくなって、自分と結婚せざるを得なくなると思い込んでいるのは、確かに単純過ぎるが、そもそも段階でのカウフマンはもうまともな人間ではなくなっているのだ。
カウフマンが良心の呵責に目覚めるのはまだずっと先のことだ。

アドルフに告ぐ(1) (手塚治虫文庫全集) [ 手塚 治虫 ]

アドルフに告ぐ(2) (手塚治虫文庫全集) [ 手塚 治虫 ]

アドルフに告ぐ(3) <完> (手塚治虫文庫全集) [ 手塚 治虫 ]
スポンサーリンク
それにしても手塚治虫という人は
このように「アドルフに告ぐ」にはこんな僕でもいくつか不満があって、中にはかなり本質的な不満もなくもないのだが、それらを差っ引いても、やはりこの「アドルフに告ぐ」はとてつもない名作中の名作。まごうことなき手塚治虫の最高傑作であり、日本の漫画の最高峰との評価は微塵も揺らぐものではないと確信している。
前にも書いたが、僕はヒトラーとナチスを描いた映画を含めたありとあらゆる媒体の中の空前の最高傑作と信じて疑わない。
こんな奇想天外のストーリーを良くぞ思いついたものだ。それを膨らませて、様々な登場人物を配置させ、それらが全て一本の骨太のストーリーとなって展開していくあたり、本当に舌を巻くしかない。
また「あとがきにかえて」から引用すると、手塚治虫はヒットラーにユダヤ人の血が混じっているということがすごく面白いと思ったとある。そして「それを証明する文書があるというのは僕が作ったフィクション」だと書いている。この極秘文書の行方を巡って物語は大きく動くわけで、この一点だけでも手塚治虫の天才を痛感させられる。
色々な断片を盛り込んでいったようだ。「僕にとって懐かしい町である神戸を舞台にしました」とも。かねてより興味のあったゾルゲを登場させたかったとか。
そういう一つ一つの細切れの情報、いわば断片を寄せ集めてきて、こういう骨太の一つの壮大なストーリーにまとめ上げる。すごいなとしかいう言葉が見つからない。天才とはこういうものだろうか。そら恐ろしくなる。
スポンサーリンク