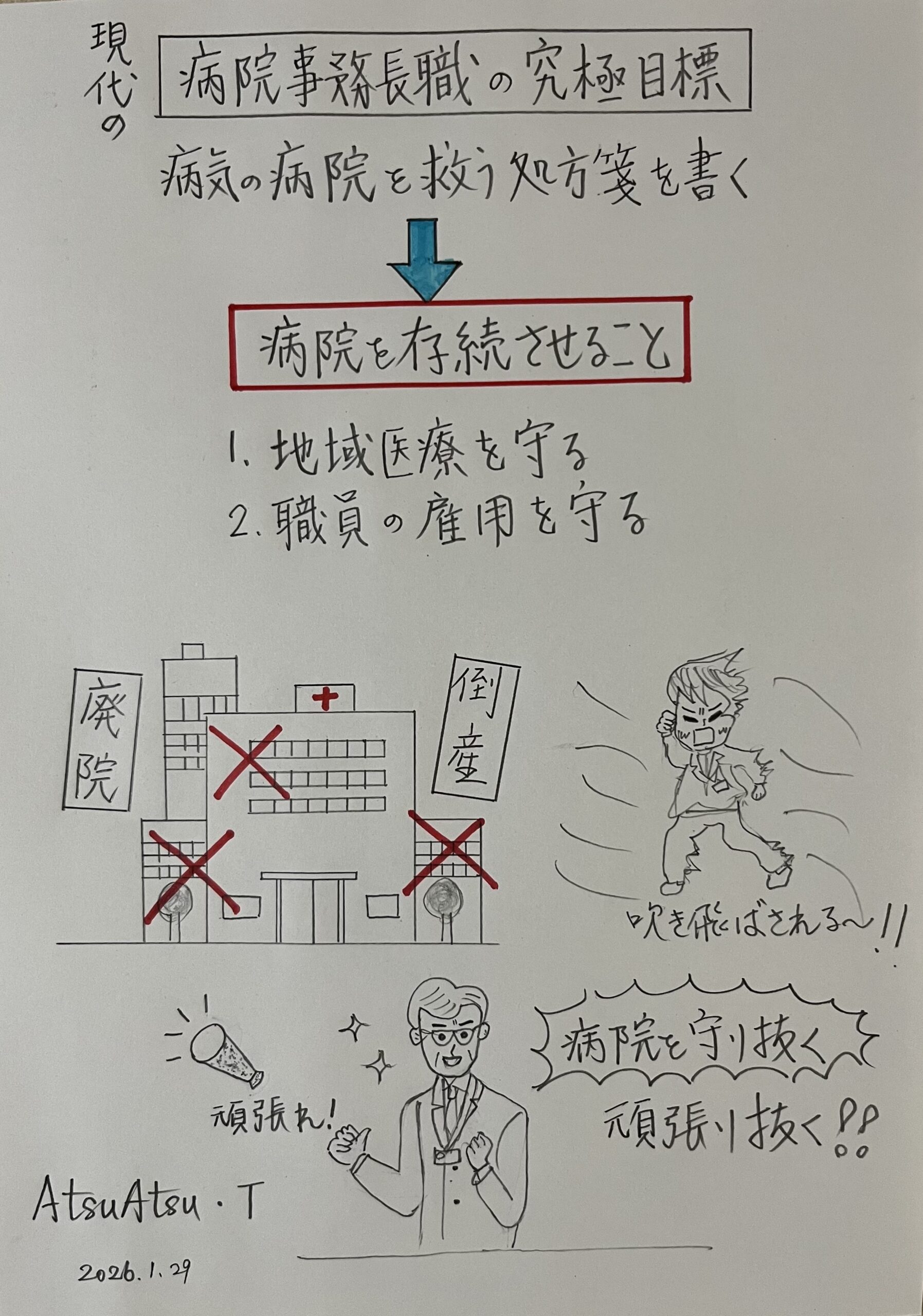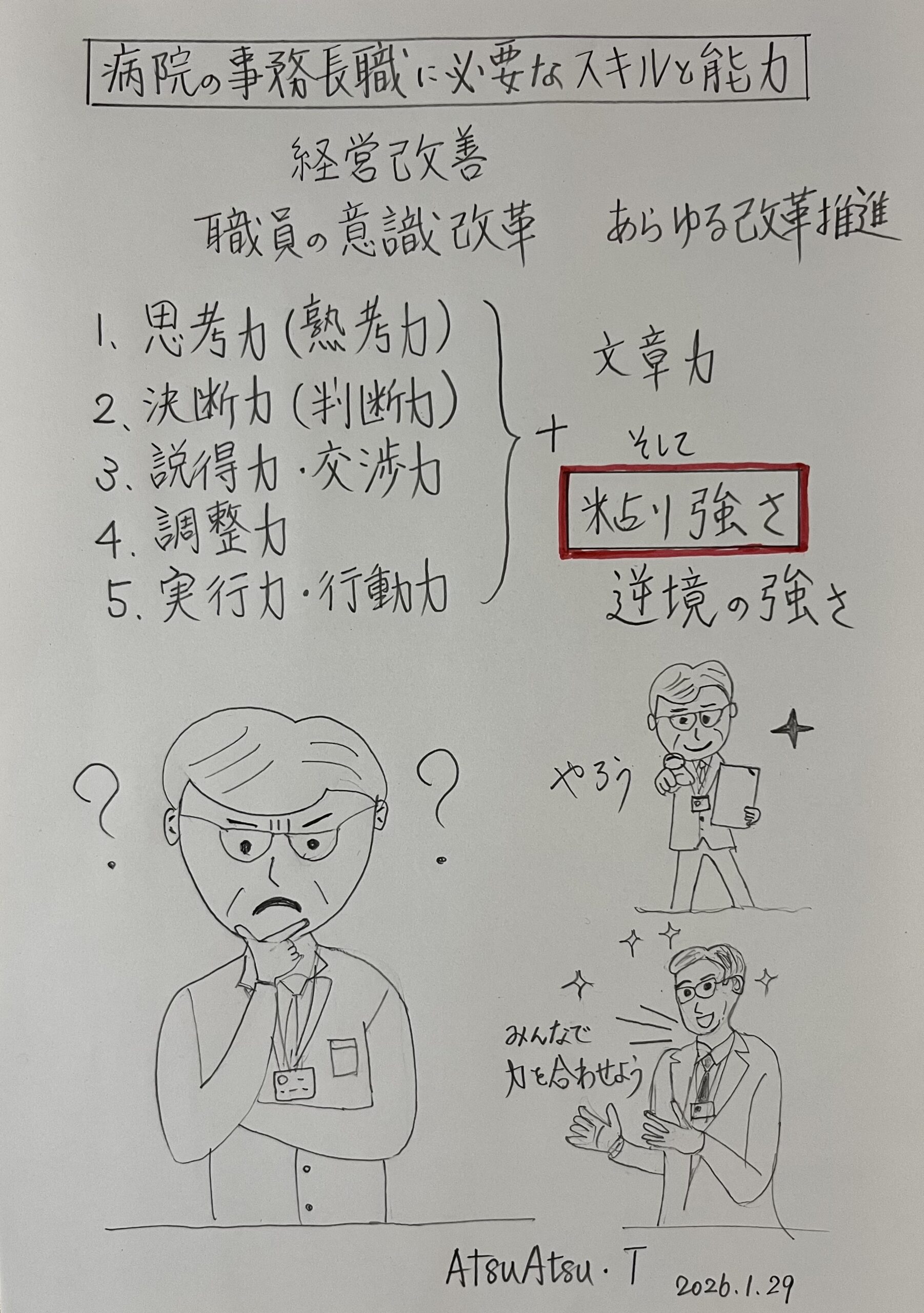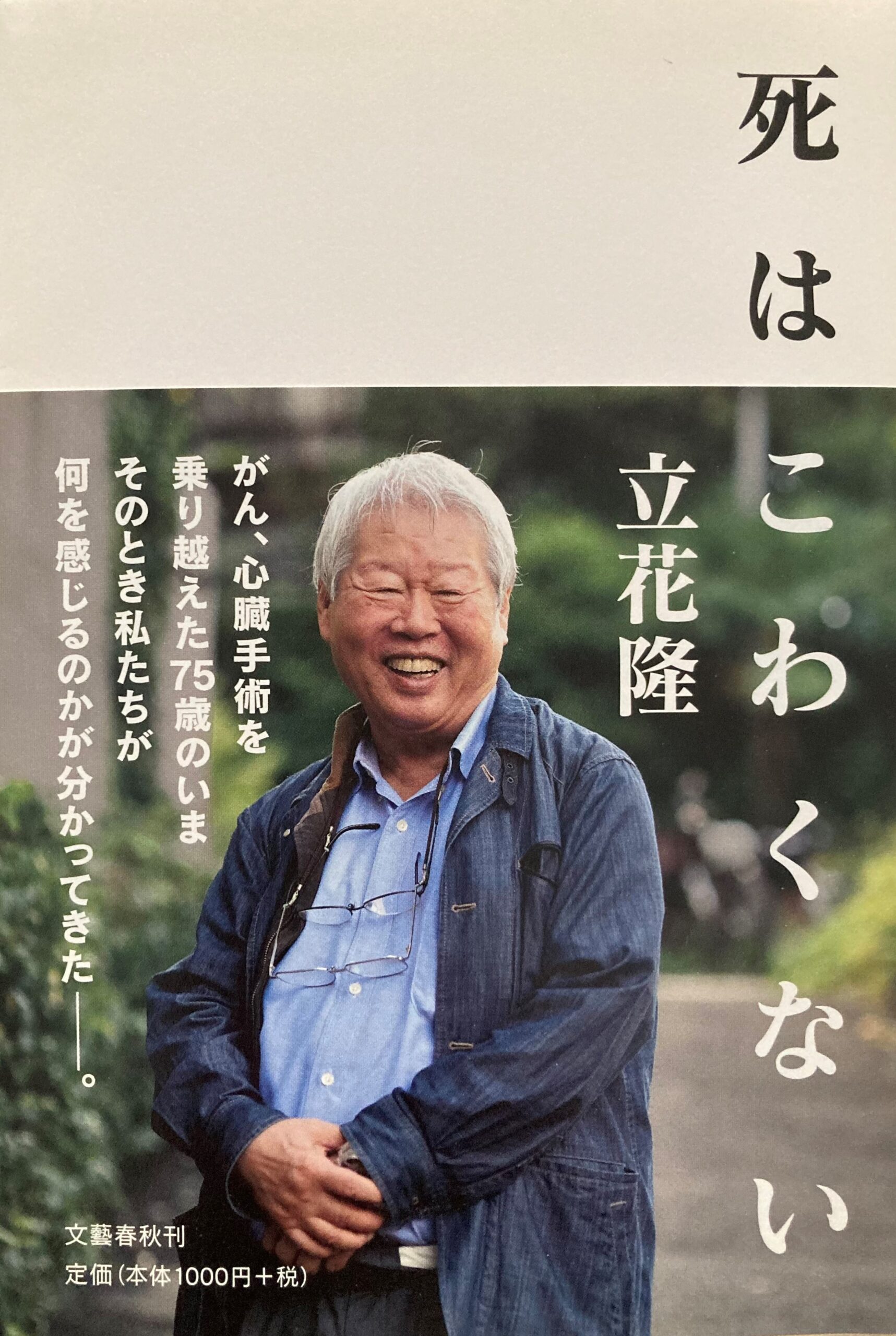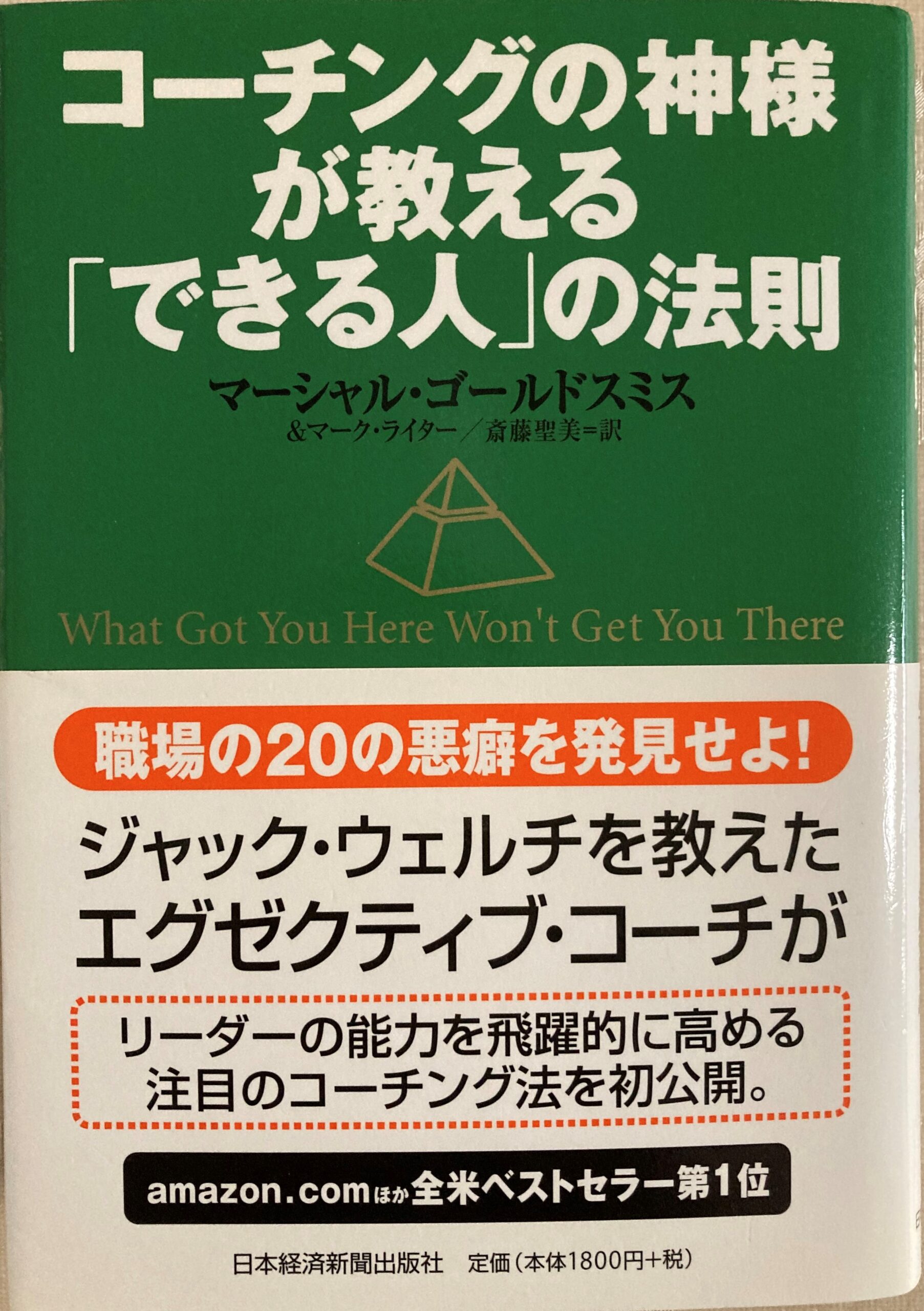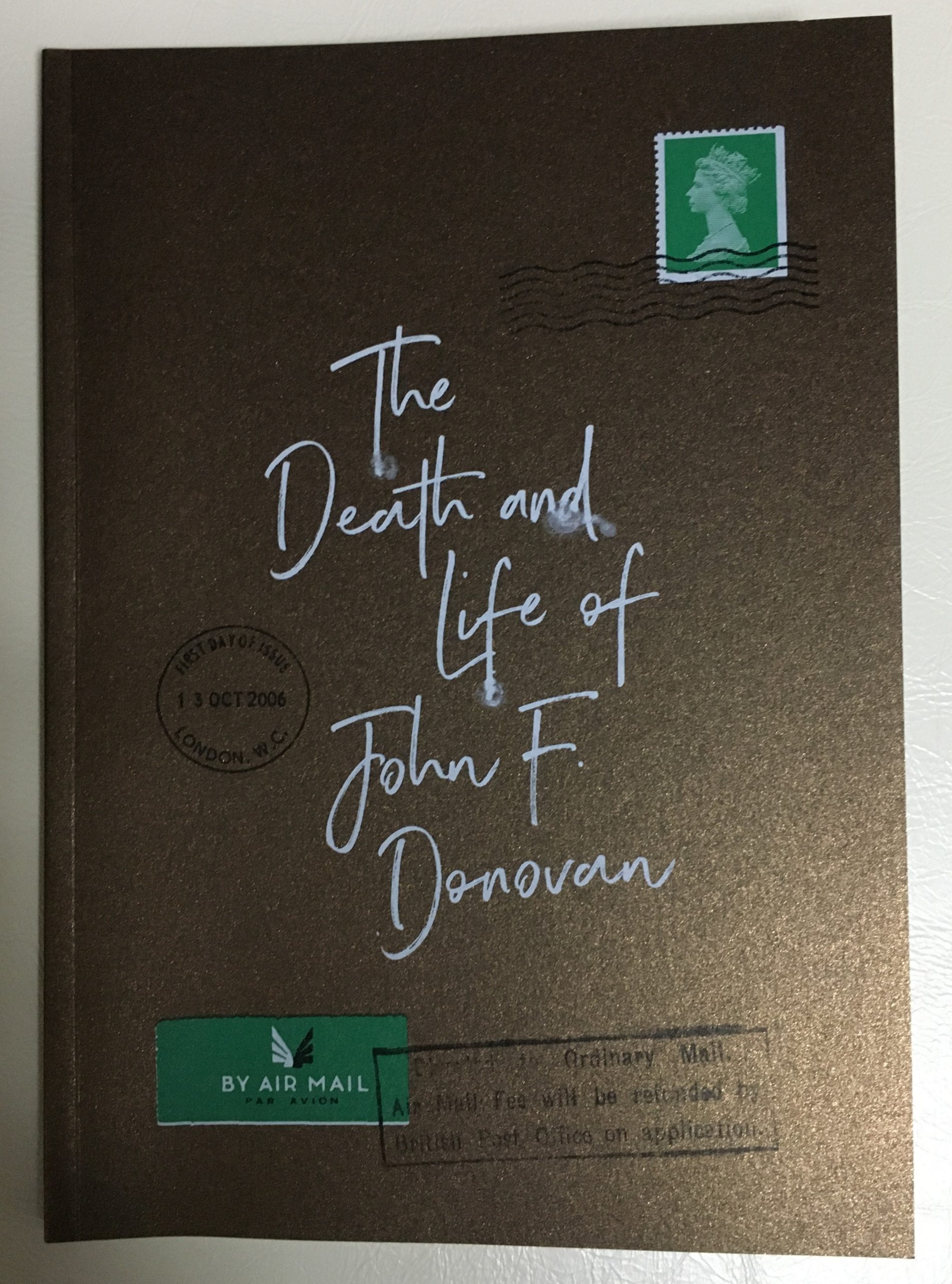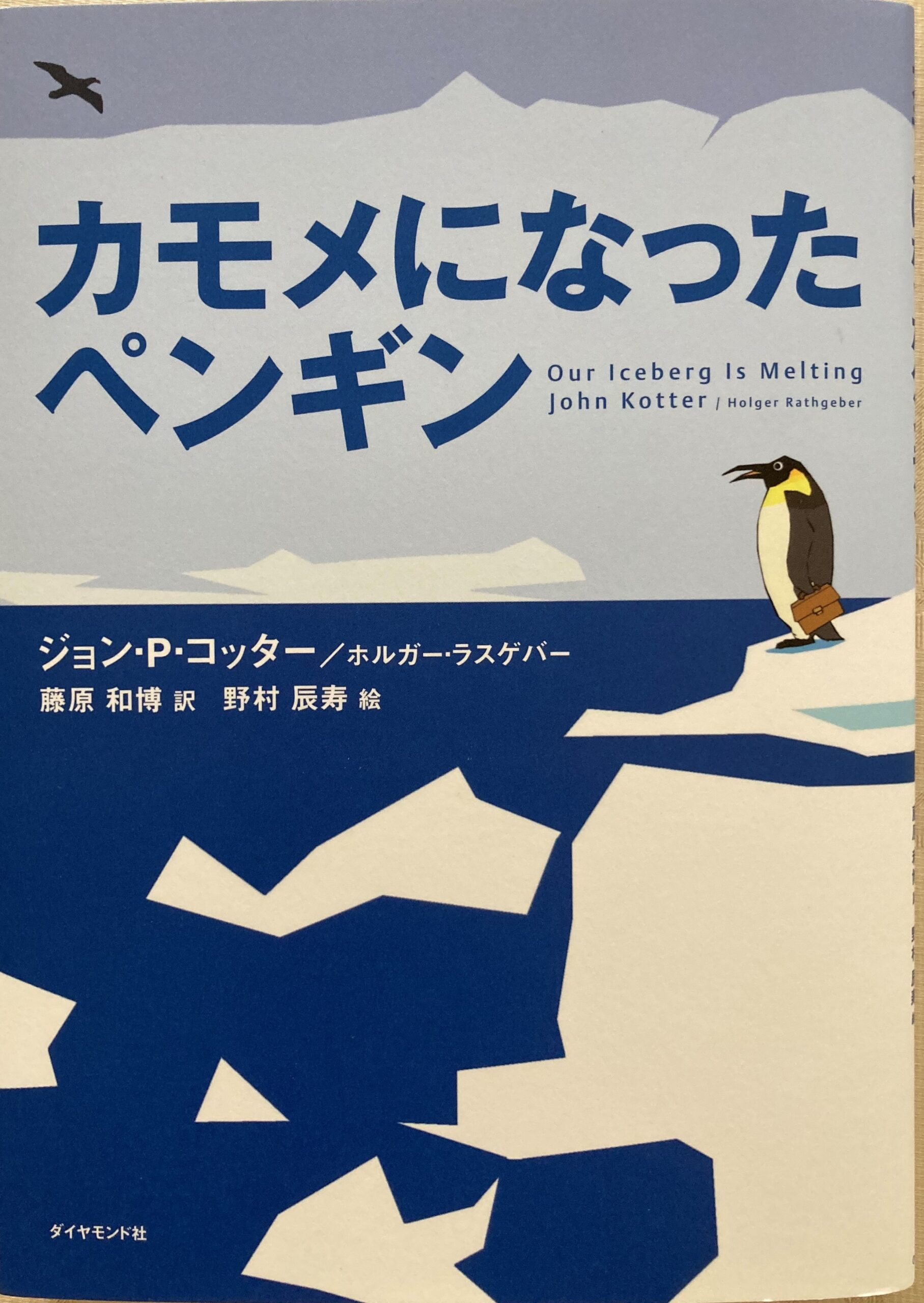目 次
立花隆の死がジワジワと堪え始める
前回、長年に渡ってその著作を読み続け尊敬と敬愛の対象だった立花隆の訃報を聞いても、僕は意外にも思ったほどには動揺せず、比較的冷静だったと書いたばかりだったが、あれからしばらくしてジワジワと深い悲しみに襲われつつある。堪え始めている。
不思議なものだ。確かに、ほぼ天寿を全うしたと言える年齢であったことと、亡くなることをある程度は覚悟していたことで、その死の衝撃と悲嘆から免れることができたと思っていたのだが、それは痩せ我慢だったのかもしれない。
前回紹介の「死はこわくない」を一気読みすることで、あらためて失ってしまったものの大きさを痛感させられている。
心の中にポッカリと空いてしまった大きな空洞を埋める手筈がない。この喪失感。立花隆ロスは、中々穴埋めできるものではない。
方法はただ一つ、残されている未読の立花隆作品をひたすら読むことだけ。
ということで、あれ以来ズッと読み漁っている。
今回は、『「戦争」を語る』である。
スポンサーリンク
直ぐに読み終えてしまう短くて薄い本
前回紹介した「死は怖くない」と全く同様の、本当に立花隆らしくない小さな薄い、直ぐに読めてしまう本である。
「死はこわくない」に続いて2016年7月に文藝春秋から出版されたもので、前回指摘したように少し変わったサイズ。普通の新書と同じ高さだが、横幅が新書よりも1cmほど広い変形版。
「死はこわくない」は現在、文春文庫になっているので、この『「戦争」を語る』も当然、同様に文庫化されていると思っていたら、さにあらず。何故か文庫化されておらず、少し入手しにくくなっている模様。残念なことである。
幸い、電子書籍は簡単かつ確実に入手できるので、そちらで読んでいただく方がいいかもしれない。
ページ数も同様だ。「死はこわくない」は189ページしかなかったが、今回の『「戦争」を語る』は、それよりはホンの少し長くて199ページ。200ページを切る薄っぺらい本である。
文字の大きさがかなり大きい点も一緒。「死はこわくない」のあまりにも大き過ぎる余白はなくなったが、今回は立花隆の家族の座談会が掲載されており、これが直ぐに読めてしまう代物。立花隆作品としては、いかにも物足りない。
この本もやっぱり、かつての精力的な活動がすっかり影を潜めた近年を象徴するかのような本と呼ぶしかないのは事実である。
本当にこれも2時間もかからずに、簡単に読めてしまう。ハッキリ言うが、本当に立花隆の他の力作を読んだような達成感には程遠い。
だが、それはそれとして、晩年の優しい立花隆に接するには貴重な本ではあるのだ。そう思わずにはいられない。

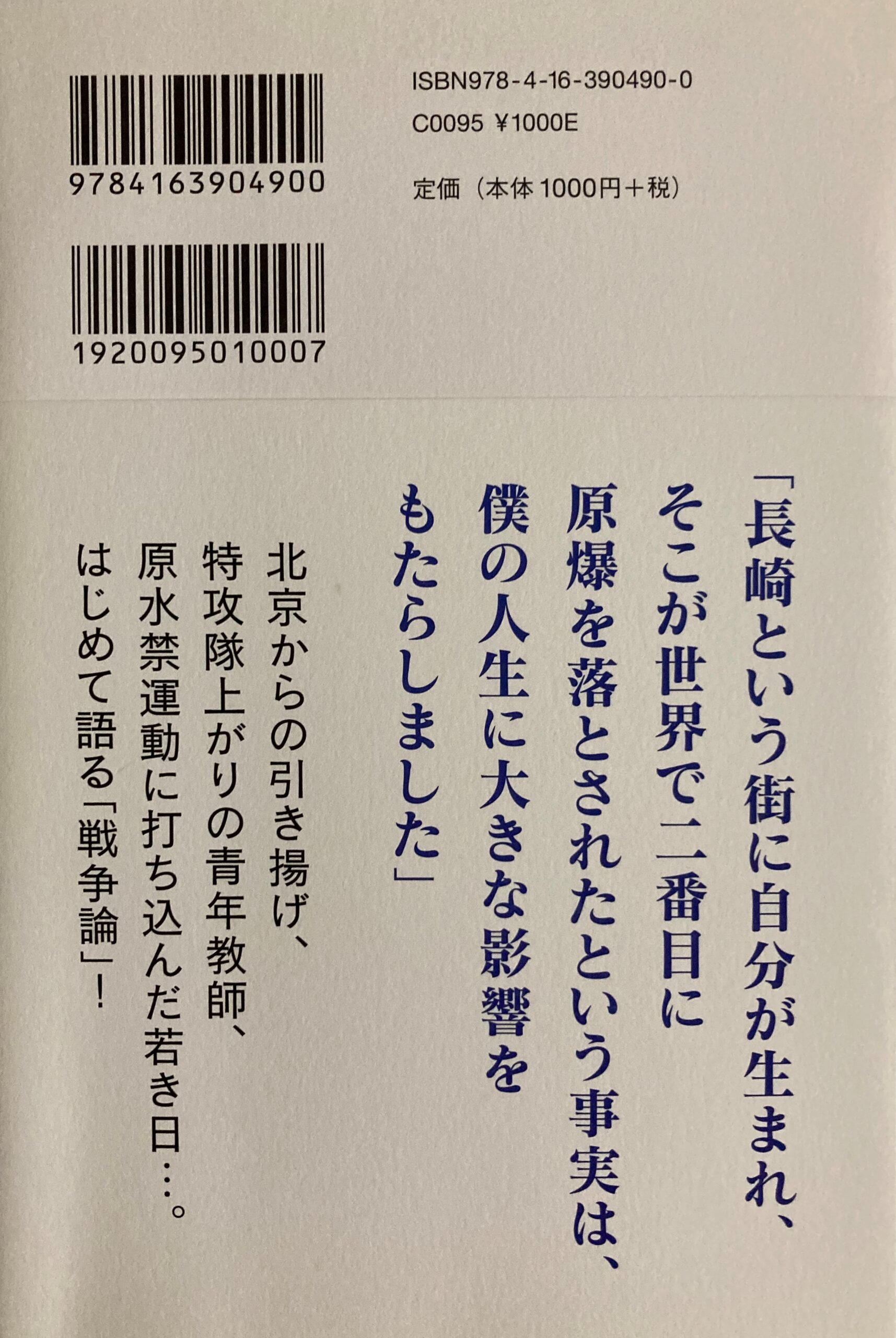
スポンサーリンク
「戦争」について語るというより、自らと家族の戦争体験を語った本
立花隆はあれだけ様々なジャンルの本を書いてきたにも拘わらず、本来は非常に興味を持っていたはずの「戦争」については、まとまった本を遺していない。これは実に不思議なことだ。
立花隆は戦争には非常に深い関心を持っていて、例えば立花隆の最大の長編にして最高の力作と評するべき「天皇と東大」は、日本がどうして国を滅亡へと導いてしまったあの戦争に突入してしまったのか、それをトコトン追求するという一心で書かれた超大作であった。だから立花隆が戦争について書いてこなかったというのは正確ではない。
とは言っても、ズバリ戦争そのものについて真正面から取り組んだ本がなかったのは、これもまた事実である。だから今回のこの薄っぺらい本が、立花隆が初めて書いた戦争の本というキャッチコピーは間違いではない。
だが、立花隆の熱烈なファンにして、戦争そのものにも何よりも強い関心を持っている僕としては、2時間程度で読めてしまうこの薄っぺらい本が、立花隆が初めて書いた戦争の本というキャッチコピーを大々的に展開するのは歓迎したくない。
この本は、「戦争」の本質やどうして人は戦争をするのかという点などを掘り下げた「戦争論」では決してなく、あくまでも実際に経験した「戦争体験」を語った本なのである。
そういう本だということを前提に読んでもらえれば、これはこれで非常に親近感の持てる貴重な本ということになる。
等身大のありのままの立花隆と接することができる他にはない貴重な本と言っていいだろう。
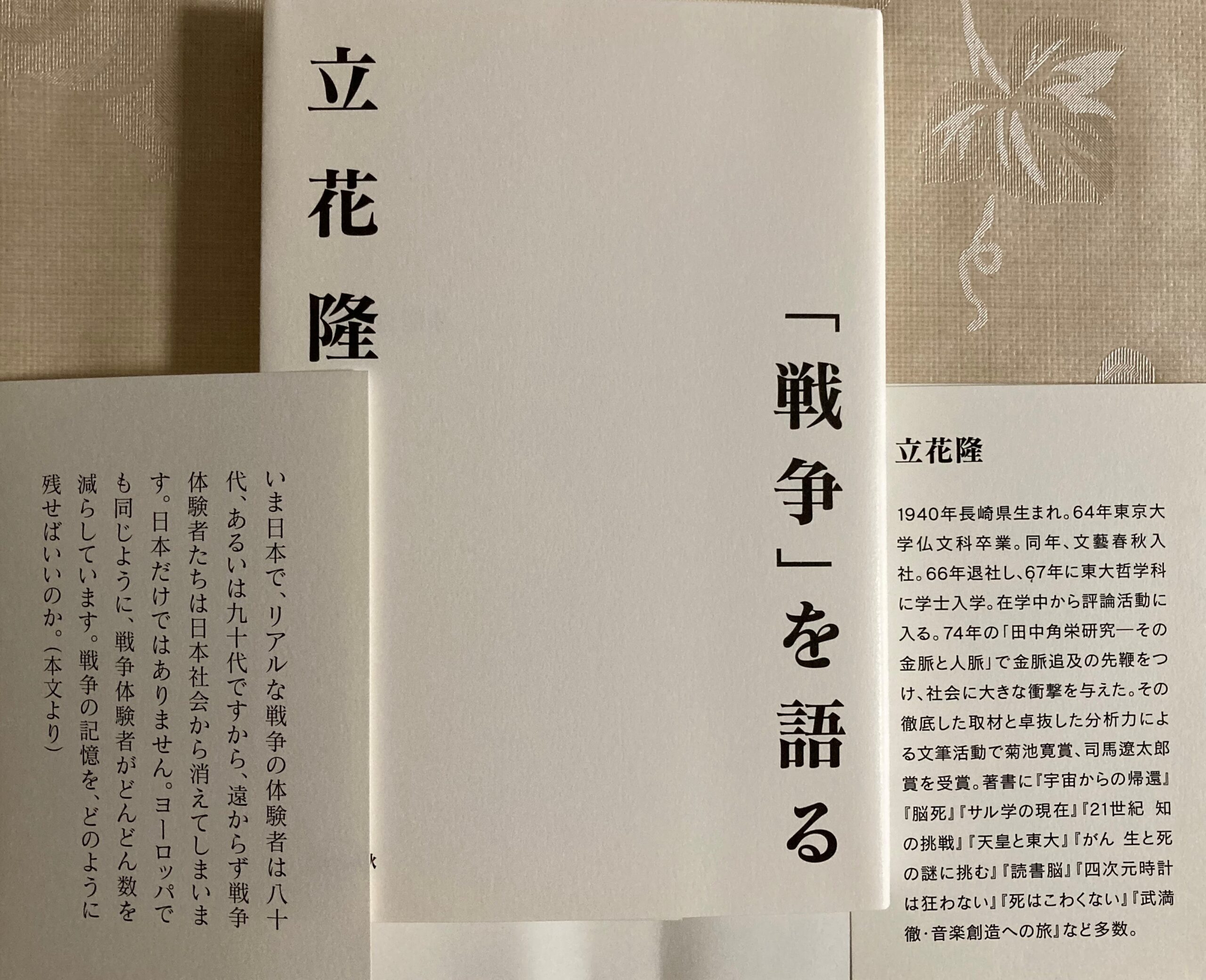
「戦争体験」って、実際に何が書かれているのか
全体は4つの章から成っている。
第一章 少年・立花隆の記憶
第二章 「戦争」を語る、「戦争」を聞く
第三章 おばあちゃん引き揚げ体験記(文・橘龍子)
第四章 〔橘家座談会〕敗戦・私たちはこうして中国を脱出した
この目次と言うかタイトルを見れば、この本がどういう内容なのか、直ぐに理解してもらえるだろう。
内容は大きく2つに分類できる。
前半は立花隆自身の自らの戦争との関りを自伝のように振り返っているものだ。立花隆が終戦を迎えたのは5歳の時のこと。その後の戦後の復興の中で橘少年がどういう少年時代を過ごしたのかということを、当時撮影された写真と自らの記憶をたどりながら振り返る。
第2章が非常に重要な部分となる。東大の学生だった若き日の原水爆反対運動に携わった貴重な体験談だ。
これは非常に興味深く感動的な内容なのだが、ここに書かれていることは、立花隆の愛読者なら誰でも知っていることで、特に僕が非常に気に入っている例の立花隆自伝と呼ぶべき「知の旅は終わらない」(文春新書)の中で書かれているものばかり。
ハッキリ言うと、「知の旅は終わらない」の方がズッと詳しく書かれているので、今更これを読んでも「知の旅は終わらない」を既に読んでいる読者には、新鮮なものは何もない。
とすれば、この本の魅力は一体どこにあるのだろうか?
それは正に後段部分にあるのである。
スポンサーリンク
立花隆の実母の文章と家族座談会が絶品
第三章は目次に明確に書いてあるように、立花隆が書いたものではなく、立花隆のお母さん、橘龍子によって書かれた、敗戦を迎えた際の、中国からの引き揚げ記である。10ページ程の短い文章であるが、非常に読みやすく、人柄を彷彿とさせる誠実な文章で、僕は大いに唸ってしまった。
この母にしてこの子あり!と言いたくなる。96歳の天寿を全うしてお亡くなりになったのだが、実に読み応え十分の貴重な一編。
そして、最後は立花隆一家による家族座談会。終戦を北京で迎えた一家が、中国から引き揚げた際の一部始終を、家族で様々な記憶をたどりながら、当時を振り返る。この家族座談会に登場するのは、司会と進行役を務める立花隆と、三章で引き揚げ記を書いている母親の龍子さんと、立花隆のお兄さんである橘弘道さん。
そして影の主役はこの座談会の段階では既に亡くなっていた立花隆のお父さんと言えるかもしれない。発見された父上の日記と小説が、当時を振り返る重要な資料となる。
この本書全体の半分近くを占める家族座談会が非常に貴重な読み物だ。ただの家族での思い出話を収録したものではないことを言っておく。この頃、立花隆が力を入れていた戦争体験を記録に残すという目的のために、立花隆が教鞭を執っていた立教大学のゼミで正式に行なわれたものである。
すぐに読めてしまうものだが、これは非常に得がたいもの。あの「知の巨人」立花隆が「おにいちゃん」と呼びかけるところなど、引き揚げのエピソード以上に、僕なんかは色々な意味で感無量となってしまう。
いい家族だなってしみじみと思う。立花隆の膨大な量に及ぶ他の作品では決して味わうことのできない、貴重なものだ。
亡くなった立花隆を偲ぶには最適な一冊なのかもしれない。
☟興味を持たれた方は、こちらからご購入を。
1,100円(税込)。送料無料。電子書籍は1,050円(税込)。本文でも聞いたが、単行本は入荷に時間がかかりそう。電子書籍の方が確実だが。

「戦争」を語る【電子書籍】[ 立花隆 ] スポンサーリンク